ロマネスク美術館 Museum of Romanesque Art (MORA)

Solignac 身廊ドーム天井
教会堂天井の架構
ロマネスクの教会堂の天井を石材で覆う場合には一般的にトンネル・ヴォールトが用いられましたが、フランスの南西部地方に複数のドームで架構された「ドーム式教会堂」ともいうべき一群の教会堂があります。
ドーム天井をもつ建築はローマのパンテオンに代表されるように古代ローマの円堂建築に多く見られ、そこでは円堂の外壁となる円筒形の壁の上にドームが載せられています。
また、円筒形の壁ではなく4本の柱でドームを架構するやり方もあり、ギリシア十字形の平面をもつビザンチンの教会堂に用いられました。
後者の場合、4本の柱で形成された方形の空間上に円形のドームを架けるには、方形の四隅上部に扇型の支えを設置して八角形を形成しドームの土台とする方法があり、ササン朝ペルシャを起源とするとされています(スキンチ)。

Poitiers St.Hilaire スキンチ
また、4本の柱間にアーチを架し、その上部に三角状の凹面を配して円を形成しドームの土台とする方法があり、後期ローマ帝国からビザンチンで多用されました(ペンデンティヴ)。

Solignac ペンデンティヴ
これらの工法はドームの荷重を4本の柱に分散することができるため、巨大なドームを架構することができ、広大な空間をつくることを可能にしました。
ヴェネツィアのサン・マルコ寺院はペンデンティヴによる5個のドームを有するギリシア十字形の集中式の教会堂ですが、コンスタンチノープルにあった聖使徒聖堂を模したものとされています。
ロマネスクでのドーム天井の採用
ロマネスクの時代にも、まれに建築された集中式の円堂やギリシア十字形の教会堂でドーム天井を見ることができます。

Neuvy St.Sepulchre ドーム

Rieux Minervois ドーム

St.Martin de Londres ドーム
しかし、ロマネスクの教会堂は長い身廊を持つラテン十字形が主流であるため、ドーム天井は正方形をなす交差部で単独で用いられるにとどまりました。

Paunat 交差部ドーム
- St.Amand de Coly 交差部ドーム
- Licheres 交差部ドーム
- Montmoreau St.Cybard 交差部ドーム
- St.Amany de Boixe 交差部ドーム
ドーム式教会堂の誕生
フランス南西部には、交差部だけでなく身廊や翼廊にもドーム天井が用いられている教会堂が見られます。
身廊をトンネル・ヴォールトで覆う場合には横方向にかかる荷重を支えるため側廊が必要となりますが、ドームで架構する場合には荷重が4本の柱にかかるため側廊が不要となり、単身廊の広大な空間を生み出すことができます。
身廊の幅いっぱいにペンデンティヴにより複数のドームを連続して架構するあり様は、古代ローマやビザンチンでは見られない、ロマネスク独特の建築様式を生み出しました。
コールのサン・ジャン(11世紀末)は1つの梁間にペンデンティヴによりドームが架されていますが、「ドーム式教会堂」の最初期の試みとされています(ルイ・ブレイエ「ロマネスク美術」39ページ)。

St.Jean de Cole ドーム
11世紀末から12世紀初頭にかけて、ペリグーのサン・テティエンヌの身廊にペンデンティヴによる2個のドームが架されました。
この新しい様式は、アングレームのサン・ピエール(交差部に1,身廊に3のドーム)、ペリグーのサン・フロン(交差部に1、翼廊に各1,身廊に2のドーム)、サントのアベイ・オー・ダム(身廊に2のドーム)に引き継がれ、身廊に複数のドームをもつ「ドーム式教会堂」の一群を生み出しました。

Angouleme 身廊ドーム天井

Perigueux St.Front 身廊ドーム天井

Saintes Abbaye aux Dames 身廊ドーム天井
また、同じく12世紀初頭、カオールのサン・テティエンヌで身廊に2個のドームをもつ教会堂が建設され、周辺のスイヤックのサント・マリ―(交差部に1,身廊に2のドーム)、ソリニャックのサン・ピエール(交差部に1,身廊に2のドーム)と「ドーム式教会堂」の建設が伝播していきます。

Cahors 身廊ドーム天井

Souillac 身廊ドーム天井

Solignac 身廊ドーム天井
なお、ル・ピュイ大聖堂では身廊に連続したドームが架構されていますが、スキンチによるもので、フランス南西部の「ドーム式教会堂」のグループとは異なる特異の様式とみることができます。

Le Pui en Velay 身廊ドーム天井
フランス南西部に広まったドーム式教会堂
ロマネスクの教会堂には様々な地方色がみられますが、フランス南西部に特色ある1グループが生まれた理由のひとつとして、ドームに使用するに適した比較的軽い石灰岩が取れることがあげられています。
開かれた身廊空間を確保したいという要求が、ペリグーのサン・テティエンヌ、カオール等の試みにインパクトを受け、その周辺に「ドーム式教会堂」の1グループを形成したものと思われます。
柳宗玄は、ジャン・スクレの「ロマネスクのペリゴール」を引用して、「構築された円蓋の数は約250,そのうち姿を消したもの約60という。その大きさは、直径12-15メートルのもの8例、8-12メートルのもの7例、7メートルのもの8例、6メートル12例、5メートル27例、4メートル70例、3メートル29例、2メートル7例‥‥という興味ある数字が報告されている」と記しています(柳宗玄著作選、第4巻「ロマネスク美術」第3章)。
フランス南西部の教会堂にドームが広範に取り入れられていたことがうかがわれます。
当美術館では、現存する小規模のドーム式教会堂のいくつかを見ることが出来ます。
・アキテーヌ地方、トレモラの2個の身廊ドーム

Tremolat 身廊ドーム天井
・ポワトゥー地方、ジャンサック・ラ・パリュの3個の身廊ドーム

Gensac la Pallue 身廊ドーム天井
Loading map...
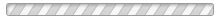
ロマネスク美術館 Museum of Romanesque Art (MORA) トップページに戻る




